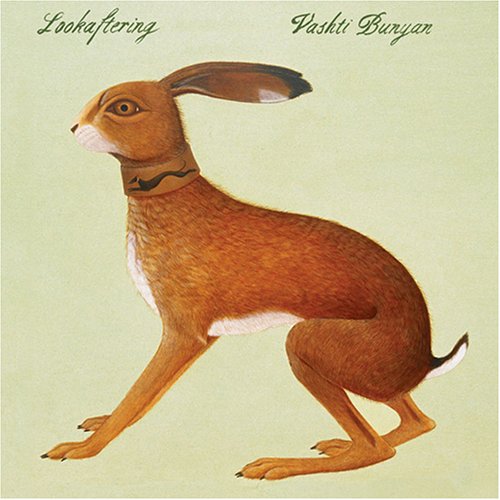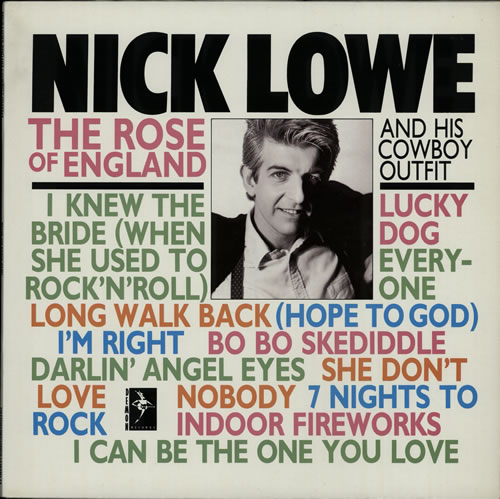emoって何?
「emo」なる音楽ジャンルが爆発的に流行していた当時、身の回りでは何をどういう定義でemoと呼んでいるのかよくわからないという人が多かった。
僕がリアルタイムで体験した2000年〜2002年くらいにおいて、「よくわからない」要因が二つあったと思っています。
1.メディアやレコ屋が「emoって言っといたら売れるで」とばかりに、こぞってemoというタームを使い始めた。
…というと意地悪な言い方になるので、「人によってemoというジャンルの解釈が違った」って感じでしょうか。
Jimmy Eat WorldからDeath Cabまで、Hey Mercedesからmatt pond PAまで、Cap’n’JazzからPedro the Lionまで、全部emoですと言われると受け手もそりゃ混乱するよね。
2.emoに括られるバンドの音楽性が変化し続けていた。
個人的にはこちらの要因が大きいと感じていて、また当時のシーンに面白さ(たまにがっかり)を感じていたポイントでもあります。
例えば、Get Up Kidsの3rdは明らかにそれまでの作風とは異なる、R.E.M.やLemonheadsのようなカレッジ・ロック・サウンドに変貌した。弾き語りで始まったDashboard Confessionalはバンド編成にシフトし大ブレイクを果たした。Sunday’s Bestはメンバーチェンジとともにソフトでメロウな面が強調され、後身バンドのLittle Onesではものすごくポップに振り切れた。
このように、同じバンドでも時期によって違うバンドかのようにサウンドが変化していって、しかもそんなバンドがたくさんいたのでemoという言葉を定義することは不可能に近かったのではと思います。
そして、音楽性が変わったバンドがいつも好意的に受け入れられるとは限りませんでした。今でも「Jimmy Eat Worldは”Clarity”までしか認めん!」という人も多いしね。
前置きが長くなりましたが、そんな賛否両論を巻き起こしたバンドの一つが、Promise Ringでした。
Promise RingはCap’n’JazzのメンバーだったDavey von Bohlen率いるバンド。00年当時の感覚では、Get Up Kids、Jimmy Eat Worldと並びemo御三家と呼んでもいい存在だったと思います。
初期は「疾走感のある演奏と泣きのメロディ」という、いわゆるemo的なサウンドでしたが、3rd ”Very Emergency”やその後にリリースされたep ”Electric Pink”辺りではパワーポップと呼んでも支障ないほどポップさが強調された作風になっていました。
そして、問題の4thアルバム(にして、ラストアルバム)の”Wood/Water”です。
初期のような疾走する楽曲はなくなり、枯れた雰囲気の楽曲が大半をしめる作品となりました。どちらかというとDaveyの別ユニットのVermontに近いような、楽曲によっては同時期のFlaming Lipsに通じるようなサイケ感も。
とにかくこれまでとは大きく変わった作品に多くのファンが困惑しました。
僕も当時はたいそう困惑しましたが、今思えば、この作品がANTIからリリースされていたのはすごく納得できるんですよね。
この作品の発売後間も無くPromise Ringは解散。
えっと、ここまでも前置きで、本題はこの後のことです。
Maritime / Glass Floor
1. The Window Is The Door
2. Sleep Around
3. Someone Has To Die
4. King Of Doves
5. We’ve Got To Get Out
6. James
7. A Night Like This
8. Souvenirs
9. Adios
10.I’m Not Afraid
11.If All My Days Go By
12.Lights
13.Human Beings
DaveyはPromise Ring解散後すぐに新バンド、Maritimeを結成。同時期に解散していたDismemberment Planのベーシスト、Erik Axelsonも初期に参加していました。(後に脱退)
アルバムは、どの時期のPromise Ringとも似ていない、Maritimeとしての個性が確立されたサウンドになっています。
とにかくメロディの良い、瑞々しいギター・ロックが並び、”Wood/Water”に拒否反応を示したファンにも納得の作品であると思います。
アルバムリリース後、2004年7月には来日公演も行われた。この時は、OwenことMike Kinsellaも共に来日してましたね。
余談ですが、この時にMarimimeのサポート・キーボーディストとして参加していたのがJeremy Garaという人物で、僕の友達がその時彼と仲良くなって、彼が参加しているバンドを2つ教えてもらいました。一つはKeplerというスロウコア・バンド。もう一つは、ドラマーとして在籍しているArcade Fireというバンド。
アルバム”Funeral”がリリースされたのは、それから二ヶ月後のことでした。